1
プロフェッショナルな知識の提供にこだわります

今やアロマテラピーに関する情報は、書籍やネットなどで誰でも知ることができます。アロマの資格も様々あり、体験やクラフトつくりなど楽しいお教室もたくさんあります。
当スクールは、施設やサークル、学校などのご要望により、そのような企画も多数承っておりますが、『手作りアロマ教室』のような趣味を広げる主旨の講座は基本的に募集しておりません。精油の特性、相性や組み合わせ、禁忌などをしっかりお伝えし、継続して学び、知識と技術を身に付けるアロマテラピーのプロフェッショナルを育てるスクールです。(ハワイアンアロマ調香講座という新メニューはございます。)
アロマテラピーアドバイザー、アロマテラピーインストラクター、アロマセラピスト、アロマテラピーコーディネーター…
様々な資格がありますが、日常で本当に精油を使いこなせている人、質問に対して的確なアドバイスができる人、医療や介護の現場であってもさまざまな方に根拠をもった精油を選び、アロマテラピーを施すことができる人などが実際にはあまりにも少ないように感じます。
アロマテラピーとは、芳香療法のことです。医療行為ではありませんが、療法である以上、「体に良いらしい」、「この香りが好き、、、」を踏まえながらもそこから卒業し、効果や効能、心身に及ぼす影響のメカニズムなどをしっかりと身に付けていただくことにこだわっています。
2
プラクティカルな利用法にこだわります

プラクティカルとは実践的、実用的という意味です。自宅にあるもので自分で作れる便利グッズなどを各講座でお伝えしたり、サロン開業の方に実際に役立つ方法をお伝えしています。
プライマリケアに関しても、寝たきりの拘縮がある筋緊張の高い方にエステ的な全身施術などはできません。そんな病態の方にどのような部位のどのような施術ができるのか、実践的にアロマテラピーを実施できる手技や内容をお伝えしています。
精神的に、肉体的に、好みで楽しむ趣味的に、目的や体調により、選ぶ精油も施術の仕方も、効率の良い利用方法も違います。通り一遍に本を読むだけや、『アロマテラピーの基礎講座』などに顔を出す程度では到底使いこなせないのが精油です。
そして、プラクティショナーは、ただ机上の知識があればいいものでもありません。医学的な要素、福祉的な要素、ストレスマネジメントの要素、栄養学、健康学の要素、様々な知識や具体例があって、理解をし、納得をし、実践することに意味があります。
講座別に、
- ・家族や自分の美容と健康やストレス解消のため
- ・医療従事者の方々が、現場で実践できる方法
- ・エステサロンや代替療法の現場にアロマを取り入れる方法
など、それぞれの用途と現場に合わせた、プラクティカルな利用方法にこだわります。
3
独自の資格制度で差別化にこだわります
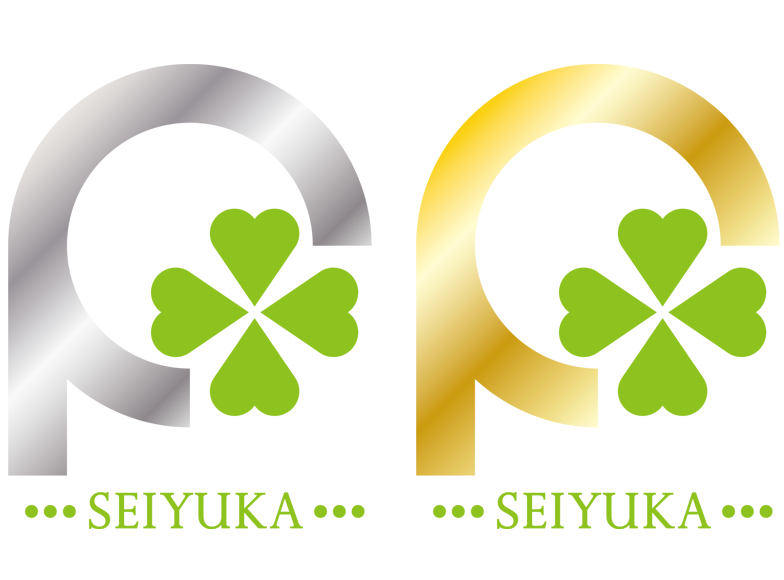
『プライマリケア アロマプラクティショナー®』とは、SEIYUKAが有する登録商標の資格名称です。総括的に、全人的に、第一線としての入り口として、あらゆる状態に対応したアロマテラピーを実践する者という意味があります。
プライマリケア医、プライマリケア学会など、医療的な要素に多々使用される言葉ですが、プライマリという言葉には様々な意味があり、基礎の、基本の、もっとも重要な、一番大切な、主役、ゲストなどの意味をもつ言葉です。
アロマテラピーを、健康な方のリラックスやリフレッシュ、美容などに適応されるものと差別化し、医療や介護の現場で実用的に実践できるスキルをもつスペシャリストを目指した資格です。
セラピストと言ってもエステティシャンと同じような業務につかれているかたもいます。SEIYUKAのエステも定評がございますが、SEIYUKAではエステ要素と、プライマリケア対応要素をしっかりと分けております。
末期がんの方が緩和ケアの一環としてアロマテラピーをして欲しいという要望に、どれだけのセラピストが、安全に、効果的な施術ができるでしょうか。また、施術ができない場合、どのようなアロマの使用方法が出来るでしょうか。
介護福祉士さんや看護師さんが、セラピストの資格を取るカリキュラムを見ると、エステ要素が強く、実際に知りたいこととやりたいことが学べないというお声がたくさんありました。
そんなニーズにぴったりの知識と技術を学びます。プロフェッショナルなセラピストが、さらなる飛躍と自己向上のためのスキルアップができる内容にこだわります。
4
(公社)日本アロマ環境協会の資格対応コースにもこだわります

(公社)日本アロマ環境協会には、たくさんの認定校・認定教室があります。アロマテラピーアドバイザー資格に対応したコースは各校様々な工夫をしています。授業料や日数、一回の授業時間もそれぞれ違います。
本来、アロマテラピー検定1級の資格は、テキストの範囲でしか出題されません。しかし、ここで学ぶ精油は世の中にある精油の一部です。
本講座は、このテストに合格することを目指した内容に他なりませんが、資料や余談の中にたくさんの情報を組み込むことで、幅をもった授業にすることにより、出題の範囲への理解もさらに深まるようにご説明しています。
独学でも受けることができる中、あえて認定教室に通う意味は充分にあります。その理解や知識の差は、その後のアロマテラピーの実践者としての差として現れます。
昔、歴史の年号を語呂合わせで覚えたような感覚工夫や、香りにもイメージを持たせる訓練などを繰り返し行います。香りの嗅ぎ分け出題対策としても、実際に精油を使い、原液・希釈時・揮発した後の残り香なども体験できるよう徹底して行います。
瓶のふたを開けて香りをかぐだけであれば、自宅で1人でできますし、区別しにくい香りの嗅ぎ分けをする訓練にはならないと考えます。
7、8時間などでは到底消化できないため、本校は少々トータル時間が長い設定になっています。習うのであれば、しっかり実力として身につける!にこだわります。
5
生徒さんへのお得なメリットにこだわります

アロマテラピーで使用する精油や基材は、比較的安価なものから大変高価なものまであります。小売りの現場ではなかなか割引になりません。
当教室の受講生には、少しでもお安く揃えられるよう、割引販売をしております。教材、粧材、基材はもちろん、ご提供したドリンクや健康によい食品なども、希望があればみんなでまとめて購入したりなどもしています。
しかしこちらから営業目的で販売、斡旋をすることはありません。あくまでも生徒さんが少しでもお得にたくさんの機会に恵まれるよう、努めています。
生徒さんがお友達や家族をご紹介してくださった場合も、プレゼントを用意しています。
生徒さん自身の施術やフェイシャルを体験されたいときは、「初回受講生特別割引」を適用できます。アロマの施術を体験することで、心地よさや効果を実感でき、ますます興味や学びの意欲が湧くと好評です。
SEIYUKAで学べてよかった!と振り返っていただけるよう、たくさんのメリットにこだわっています。
6
講座終了後のアフターフォローにこだわります

アロマテラピーアドバイザー、アロマプラクティショナー、アロマセラピストとしてのスキルアップなど、全ての講座において(1日単発のイベント授業は除く)終了されたあと、まだまだプロとして独り立ちをするのに自身がない…という方にも引き続き、アドバイスや講義のプロデュースなどを行っています。
ご質問や個人指導、補講などもご希望に合わせてできる限り対応いたしております。メーカーの中には取引をする際に、まとまったロット数でしか卸売りをしないところもございますので、生徒さんには商材を割引価格にてお譲りしています。
卒業生の方が開業し、お客様が増えて、やっと自分であれこれやれるようになりました!というような報告をもらう時が一番うれしいものです。
スクールとしても、サロンとしても、卒業された方々が独り立ちして成功されるよう、また、仕事やサービスにやりがいをもって楽しく充実した事業ができるよう、フォローさせて頂こうとこだわっています。
7
知るだけではなく、教えられる人材を育てることにこだわります

例えば、アロマテラピーアドバイザーになられた方が、自分もアロマの教室を開きたい!と計画されても、なかなか自信がなかったりします。
受講するときは生徒としての心構えと知識取得に必死だったけれど、教える側としての技術や話術、心構えとなると、受講生時期とはまったく違うものです。
時間の配分、質問への応対、興味をひく内容、わかりやすい説明、正確な知識、、、などなど、責任も出てきます。スキルを盗んでいただき、参考になるところを再確認するという意味で、「講習の見学制度」がございます。
同じ内容を伝えるにしても、表情、声色、スピード、雑談や余談、間合い、生徒さんへの振り、様々な要素でスクールの特色はまったく違うものです。
自分らしさを大切にしながら、ご自分の良い面を伸ばしながら、自信のない部分をクリアできるように参考にしていただけます。もう生徒さんとしてではなく、同じ講師の立場で、先輩の授業を見学する、という気持ちで望んでいただけます。なかなか他にはない制度ですから卒業生の方にはぜひ使ってもらいたいこだわりのサービスです。
授業そのものも、ただ教えるということではなく、皆さんが生徒さんに教える場合、ここだけはしっかり伝えてください!とか、これはちゃんと理解しておいてくださいね!と、教える立場になった場合の指導を入れています。
本当に役立つ正しい知識を広め、教える立場のプロフェッョナルな人材を養成することは、これからの少子高齢化介護大国、ストレス社会においてもアロマテラピーがますます期待される中において急務であると思っています。






